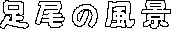足尾町散策
(11)8月31日 初秋
1. 石仏のある空間
今日の最初の被写体は
“石仏”でした。日足トンネルを足尾側に抜け、しばらくして私道と思われる脇道に入ると、いきなり行き止り。個人宅の庭でしょうか、オオハンゴンソウの花が咲き乱れるなか、何体かの石仏が並んでいました。
背景に咲くオオハンゴンソウとの組み合わせで、初秋の彩りを添えた石仏撮影ができました(このページのトップ写真:2025/08/31)。
この場所では心が癒され、石仏の魅力を発見することができました。

2. 蔦 の からまる古河橋
秋色した鉄サビの古河橋にからまるツタの葉と、手造り的な鉄の肌のシルエットには存在感が溢れています(写真:2025/08/31)。

3. ブッドレアの咲く民家
今はもう秋、誰もいない家。茶色くなった花がらを摘む人の影もみえず姿もなく藤色の花が玄関先で、けなげに咲いています(写真:2025/08/31)。

4. 廃屋
赤倉地区にてスナップショット、対岸は製錬所です。この建家も静かに立ち続けています(写真:2025/08/31)。

5. 大煙突と菊芋
大煙突を背景に咲く黄色い花、“キクイモ”を写しました。大煙突と比較すると、さすがのキクイモの背丈も低く感じます(写真:2025/08/31)。

6. 黒揚羽と秋茜と目弾き
クロアゲハとアキアカネとメハジキの
スリーショット、愛宕下にて撮影。
(写真:2025/08/31)
☆ メハジキ(目弾き):路傍に自生するシソ科の2年草。
益母草(やくもそう)という漢名は、「母の益になる薬草」という意味で、産前産後の薬として使われてきた。
和名のメハジキは、子供が茎を短く切って、上下まぶたのつっかい棒にする遊びから、この名があるそうです。

7. 銅親水公園
公園の裏山の裏山の上にモクモクしている積雲が、初秋の爽やかさを運んできます。
(写真:2025/08/31)

8. 駒繋
愛宕下を歩いていると道路の山側にコマツナギが咲いていました。
(写真:2025/08/31)

9. 牡丹蔓
隣では “ボタンヅル”が、他の植物に覆いかぶさるようにして咲いていました。葉の形は牡丹の葉に似ています(写真:2025/08/31)。

10. 上の平
背景の山は、花戸山(945m)の尾根。花戸山から北東の方角に尾根道を進むと、 “ニタニタ峠”に出ます。
以下『町民がつづる足尾の百年』抜粋
(昭和5年当時19歳の娘さんのお話し)
『(前文略)赤倉から花嫁姿で深沢へ、深沢から山道を越えて神子内に嫁ぎました。山道でも大勢の人が通行していたので険しいとは思いませんでした。(後略)』
この娘さんが花嫁姿で越えた峠が上記の “ニタニタ峠”ですが、現在この山道は消滅しています。
(写真:2025/08/31)

11. 上の平から中倉山
今までにこの場所で何回シャッターを切っただろうか。いつも新鮮。今回は足尾の秋を代表するススキを主役に写しました。
騒がしく風になびくススキの穂が、いつもは寂しい足尾の風景を賑やかにしてくれました。
(写真:2025/08/31)

12. 朝顔
松原地区の表通りに建つ店先に、“アサガオ”が咲いていました。
(写真:2025/08/31)

13. さんしょう家
今日の昼食は、“冷し中華”を選びました。店先に出された黒板に、白墨で書かれた文字(写真右下)が目に入ったのでオーダーしました。
(写真:2025/08/31)

14. あしおトロッコ館
本館のトロッコ鉄道博物館では、鉄道模型などが展示されています。
野外展示場では各地で活躍したトロッコ及び鉱山用架空索道のバケットなどが、保存展示されています。
内燃機関車が牽引する客車に乗車してきました。
(写真:2025/08/31)

15. トロッコ列車かわせみ5020
トロッコ列車に使用されるオープン構造のトロッコ車両 “かわせみ5020”が、足尾駅の待避線で待機中です。
(写真:2025/08/31)

16. 足尾銅山記念館
赤レンガ造りの建物は、明治40年(1907)に建築された(国の登録有形文化財)“旧足尾銅山鉱業事務所付属書庫” です。
右の建物が今年8月8日から一般公開された「足尾銅山記念館」です。
“足尾鉱業所事務所”を往時の場所で当時の姿を目指して再建しています(写真:2025/08/31)。
(写真をマウスでロールオーバした時に変化する写真は、2016年7月17日に南西の方角から撮影した、“旧足尾銅山鉱業事務所付属書庫” です。)